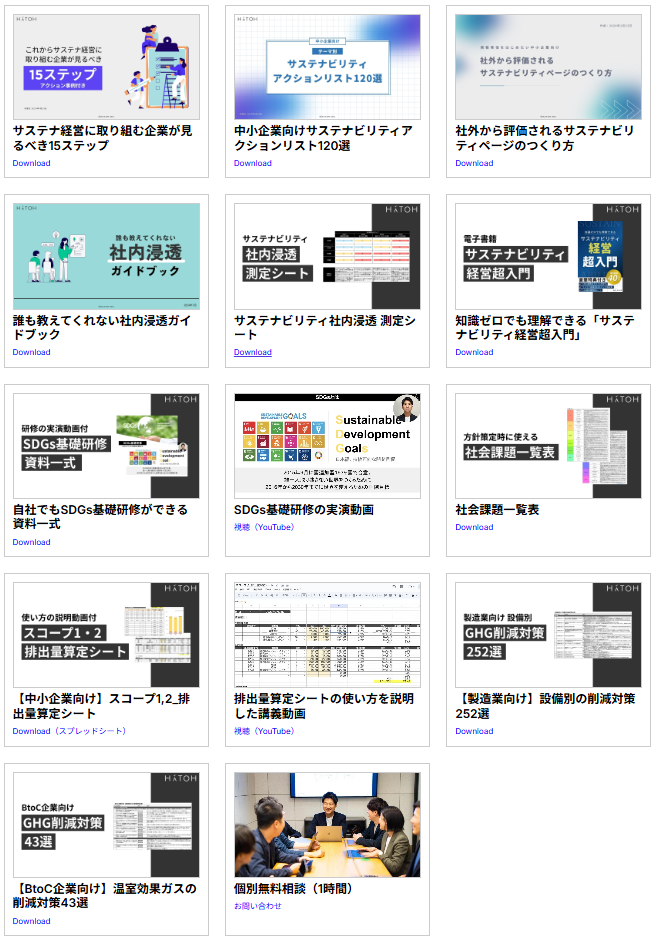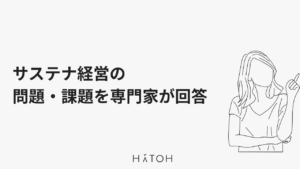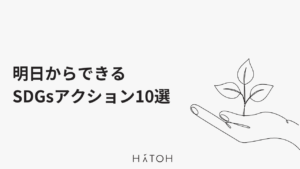本記事では、「出世させてはいけない社員の特徴」を5つに整理し、人事・管理職が現場で使える判定ポイントを示します。
あわせて、人的資本・サステナビリティの視点から「昇進基準に落とし込むべき行動指標」も提示します。
人事評価や管理職選抜のプロセスにそのまま組み込める形で、昇進ミスを未然に防ぎ、組織のパフォーマンスを最大化するための実践ガイドとしてお役立ていただけると嬉しいです。
こちらの内容はYouTubeでもご覧いただけます。
結論:誰を出世させるかが企業価値を左右する
昇進は単なる人事イベントではありません。
企業が給与・研修費などを投じる相手は「コスト」ではなく、企業価値を高める「投資対象=資本」。

誰を上に据えるかで、部署の生産性、社員のモチベーション、離職率、プロジェクトの進み方まで変わります。
チームスポーツにおける監督やキャプテンの良し悪しが勝敗を分けるのと同じで、上司の質が組織成果を決定づけます。
誤った選抜は業務停滞や優秀人材の流出を招く一方、適任者の登用は事業を押し上げ、良い人材を惹きつけます。
そのうえで、今回は出世させてはいけない社員の特徴5選を紹介します。
特徴① ワークライフバランスを「過度」に最優先する社員
働き方と私生活の両立は重要ですが、管理職には想定外への対応や部下支援が不可欠です。
「毎日必ず定時退社」といった硬直的な姿勢は現場の混乱を招きます。
重いクレーム対応直後、上司が既に退社していた。部下はそこで「この上司にはついていけない」と感じます。
ここで重要なのは長時間労働の推奨ではありません。
企業価値のために、自分のワークライフバランスを状況に応じて「柔軟に」調整できる器量があるかです。結果を出すために臨機応変に動ける人を候補にする方が良いでしょう。
特徴② 部下を適切に「叱れない」社員
上司に必要なのは、部下のモチベーションを高める承認スキルだけではありません。
態度や姿勢が緩んだ時に、行動を正すための「叱る」力が要ります。
ある調査では、20代の約4人に1人が「叱ってほしい」と考える傾向も示されています。
大切なのは、下記のようなポイントです。
①どの場面で叱るべきかの見極め
②人格否定や人前での晒し上げを避ける理性的・論理的な伝え方
感情をぶつける「怒る」しかできない人、ハラスメントを恐れて一切指摘しない人は昇進不適です。
特徴③「多様性」を理由にチーム成果に貢献しない社員
「フレックスだから午後からしか出社しない」「在宅の方がはかどるので出社しない」など、会社の許容範囲を超えて「自分の都合」だけを主張するタイプは危険です。
研究でも、この手のタイプの方は、「課題に向き合わず責任転嫁しがち」とされます。
管理職になれば、達成できない理由を環境やチームのせいにしやすくなります。
本来の多様性は「違いを活かしてチームとして成果を出す」こと。事情がある働き方でも、チームにとって価値ある成果に結びつけられるかが基準です。
特徴④ 健康管理を怠る社員
頻繁な体調不良や不規則な生活は、集中力・判断力を下げ、仕事の効率を著しく落とします。
ある調査では、こうした健康リスクは1人あたり年間100万円超の生産性を損失しているとも言われています。
ここでいう健康リスクは、花粉症・腰痛・頭痛などの「日常的不調」も含みます。
喫煙、夜更かし、慢性的な睡眠不足が目につく人は要注意。逆に、早起き・定期的な運動など、セルフマネジメントができている人は成果を出しやすく、管理職に向いています。
特徴⑤ 取引先に対して横柄な態度をとる社員
発注側の立場を背景に、取引先へ高圧的な言動を取る人はNG。
言葉遣いや態度だけでなく、過度な納期短縮・値引き要求といった不公正なふるまいも含みます。
長期的には、相手が契約以上に尽力してくれなくなり、困った時の相互支援も期待できません。悪評が広がればブランドにも傷がつきます。
社外と向き合うポジションには、双方にメリットのある提案をできる「気持ちのいいコミュニケーション」が必須。
なお、このタイプは社内上層部にだけ愛想が良い場合もあるため、不定期ミーティングの同席や取引先ヒアリングで実態をつかむことも方法の1つです。
出世者の見極めポイント
改めて、今回のNG社員の特徴を踏まえて、「出世させるべき社員を見極めるポイント」を下記にまとめます。
- 柔軟性
-
必要時にワークライフバランスを調整し、結果責任を果たせるか。
- 指導力
-
叱るべき場面の判断と、人格を傷つけない伝え方を持っているか。
- 多様性の扱い
-
自分本位ではなく、違いを活かしてチーム成果に接続できるか。
- 健康習慣
-
日常的不調を最小化するセルフケアを継続できるか。
- 社外対応
-
力関係に依存せず、公正で建設的な関係を築けるか。
今後に向けて | サステナビリティ経営の視点を昇進基準に組み込む
昇進候補者が、短期の数字だけでなく、組織の持続可能性(人材育成・働きやすさ・外部との信頼関係)をどう高めるかまで視野に入れているかを確認しましょう。
サステナビリティ経営の観点で見れば、昇進基準のヒントは他にもあります。
例えば、コンプライアンスを守れない人は論外です。不祥事のリスクは会社全体に波及します。また、女性活躍、男性の育児参加、リスキリングといったテーマに対する理解や実践姿勢は、チームの持続的成長に直結します。
このように、サステナビリティの各テーマを「昇進行動基準」に落とし込むと、人選の精度が上がります。
まとめ | 正しい人選が成果と人材流動を好転させる
誤った昇進は、業務停滞・士気低下・離職増加を招きます。
逆に、柔軟性・適切な指導・多様性の活用・健康習慣・公正な社外対応を備えた人を登用できれば、事業は上向き、優秀人材も集まります。
ぜひ今回の5つの特徴を踏まえて、正しい昇進者の仕組みづくりを進めていきましょう。
【無料】サステナビリティ経営の特典資料15点をプレゼント
今ならお問い合わせいただいた方限定で、下記の特典資料&個別無料相談を無料配布中!
✅ サステナビリティ経営超入門の電子書籍
✅ サステナビリティアクションリスト120選
✅ CO₂排出量の算定・対策シート
✅ 【製造業向け】設備別の削減対策252選
✅ 個別無料相談(1時間) など
…など、企業のサステナビリティ経営にすぐ使えるツールを無料プレゼント!
-1.png)